|
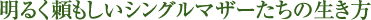 |
|
この村に住み始めたころ、昔のご同業がいた。といっても絵描きではなく、祭りで物売りをする寅さん稼業、露天商のご仁である。娘の先生役を果たしたサラの母親マリア、それと今はドイツ人の女性と結婚した旦那がまだ夫婦だったころのことだった。元ご同業とあれば親しみが湧くし仲間意識もある。すぐに、なにかと声をかけあうようになった。
八月末、ホコリだらけの赤い大型ライトバンが広場に帰ってきた。もうフェレイローラ村の夏祭りも終わり、あらかたの元村人は帰ってしまい、閑散とした広場にはシェリー酒会社の宣伝用小旗が寂しく風に揺らいでいた。泉の水音だけが乾ききった大気をどうにか和ませていた。
「日焼けしたね、どこか海辺の街に行ってたの?」
「アルメリアの祭り。潮風はきついし、日射しは避けようがないし、背中がヒリヒリするよ」
旦那は早くシャワーを浴びたいといった表情だし、マリアは寝込んでしまったサラを抱え、言葉少なげに帰っていった。
村からは東に百キロほど離れたアルメリアの祭りは、アンダルシア六県のなかでも夏の最後を飾るビッグイベントである。しかし、祭りの会場は海岸に面しており、日陰はないし、昼間の暑さは地獄である。アルメリアの内陸部は半砂漠が広がり、熱風が渦巻く凄まじい土地柄なのだ。それにテキヤ泣かせの売れない街の代表でもある。
もう四半世紀も前の話になってしまったが、オレもジプシーの家族と共に、このアルメリアの夏祭りに売りに行ったことがあった。
少し本題から逸れるが、そのころの生活ぶりを話してみたい。
当時、オレはセビリアの郊外に住み、絵筆ならぬペンチを握ってアクセサリーを作り、村祭りを回りながら生活していた。もちろんテキヤ業をしにスペインに来たのではなく、絵を描きたいからやってきたのだ。ただ、南スペインの晴れ渡った青空に、シェリー酒で乾杯し、琥珀色の輝きに酔いしれていたら、一年もたたないうちにお金がなくなってしまった。そんなとき、スペインの女神は、優しく救いの手を差し伸べてくれた。オレがスペインに恋をし、もっと絵が描きたいという想いを解ってくれたらしい。ただし、絵描きとしてでなく、祭り回りのテキヤ業で生業をたてなければならなかった。おかげで、絵描き稼業に専念するまでには、五年近い回り道をしなければならなかった。
七十年代後半、世の中はヒッピー文化真っ盛りだった。ルーズな衣装が流行り、若者は自由を謳歌していた。夜になると、繁華街では妖しげな輩がアクセサリーを売り、そのころは警察官もみてみぬふりをしていた。そんななか、日本人のテキヤ衆も何人かいた。そこで、少しはお金になるかなと、彼らの売り子をしてみたら、小遣い稼ぎになった。そこでハリガネ細工のアクセサリーはオレでもできそうだったので、なんとかスペイン滞在を延ばすために、自分でテキヤ業を始めることにした。そのうち、どうにか売れそうな商品もできてきたし、売りかたも、元外資系広告代理店で販売戦略なるマーケティング理論を頭に叩き込まれている。商品構成と価格帯を上手く調和させ、売れ筋商品を頂点に数十点揃えてみた。店は地面に直接布を敷くのをやめ、目線に合わせて机を使った。布は黒ではなく、派手な赤などを選び、夜はガス灯で明るくして客を呼び込む工夫をした。そのうちジプシー、セビリア大学の学生、旅の途中の日本人、外国人ヒッピーまで売り子にし、販売拠点の拡大を図った。おかげで、売上げはロケット的に伸びていった。一番のヒット商品は、地中海の海岸で拾った小判型の真白な石に〈愛〉とか〈幸〉と漢字で書き、その下にマリアとか名前をいれたペンダントだった。原価はゼロ、手間賃だけで面白いように売れた。
五年近く続いたテキヤ業最後の年、海岸沿いの夏祭りを追いかけながら商売をしていた。八月最後の週、オレもアルメリアの夏祭りで店を広げていた。思いだすセビリアのジプシー家族との一ヶ月に及ぶ共同生活。旦那は三十代半ばの男でエンリケという。片脚が不自由で、ぎこちない歩きかたをする。これが警察官にはいたく覚えよく、オレはエンリケの売り子という名目で、いつもお目こぼしを受けて商売をしていた。エンリケには、いまでも心から感謝しているのだが、アルメリアの祭りの最終日、忽然と姿を消してしまったのだ。売上金も商品も店のすべてを持ったまま、いなくなってしまった。昨日まで一緒に飯を食べていた仲なのに…、彼にとっては、オレはジプシーでない男、それも異邦人だからなのか、やはり寂しかった。でも、まあ、そんな盗人はいくらでもいたし、それがテキヤ商売だった。そんな輩のなかでは、底抜けに明るい屈託のない男だったから少しも憎めなかった。
彼には後日談があり、その年のクリスマス、セビリアの繁華街で商売をしていたら、またまた現れたのだ。それもオレの作ったピアスを数個、手に握ってである。
「イシーじゃないか。久し振りだね。恰幅よくなって、たっぷり儲けたな。そうだ、これ、おまえに返すよ」
「返すって、これだけ? 他の商品や売上金はどうしたんだよ」
「それがね、みんな子供のお腹に収まって、なにも残らなかったわけ。それより今度こそ、売ったお金は渡すから、もう一度だけ売り子に使ってくれよ」
少し離れたところで、旅ではご馳走になったカミさんと三人の子供たちがこちらをみている。さすがに、こんな状況では断ることはできない。再びテキヤ道具一式を彼に貸し与えてしまった。だが、結果は同じことの繰り返しだった。さすが、これには仲間のジプシーたちもオレに同情してくれた。何日か経ったら、老いたジプシーの男が商品を隠している安ホテルの住所を教えてくれた。おかげで最悪の事態は免れたが、オレにとっては裏切られたことの悲しさが先にあった。
その年をもって、オレはきっぱりテキヤ業を辞め、絵描き業に専念した。夏、セビリアの街を歩いていたら、見覚えのあるホロ付きの小型トラックが急停車した。サングラスをかけたエンリケが、元気に降りてきたのだ。
「イシーじゃないか、会いたかったよ。いいこと教えてやるよ。忙しいから手短に話すな。駄菓子屋を開いたんだ。どうにか商売になってるさ。それからな、子供がもうひとり生まれてな、男の子だよ。娘ふたりと息子ふたりの親父になってしまったさ。おまえ、テキヤ業辞めたと聞いたぞ。惜しいね、親分やってればいいのに…。元気でやれよ、幸運を祈ってるからな! アディオ!」
一家五人が生活していた小型トラックは、後続車のクラクションに追いたてられながら姿を消した。まったく、真底、楽天的な男である。持ち逃げされたお金も、どうやら正業につくために役立っていたらしい。なんだかオレまで嬉しくなったのを昨日のように覚えている。アルメリアの街にはほろ苦い、そんな思い出があった。
オレはその後、四年間はなにもせず、絵三昧の生活を続けた。足掛け十年、やっと日本に一時帰国し、遅まきながら絵描きとしてのスタートを切ったのだった。
八十年代、世の中が豊かになると、ヒッピー文化は姿を消してよりエレガントなファッションが台頭し、粗末な手作りアクセサリーは売れなくなっていた。そんな時代に、マリア夫婦はアルメリアの夏祭りに行ったのだ。もう衰退期に入っていたテキヤ業で売れない日々が続いたのかもしれない。商売が厳しくなると、夫婦仲にも問題が起きやすい。旦那は青い瞳が魅惑的なドイツ人女性と恋に落ち、ドイツに行ってしまったのである。マリアはまだ幼かったサラと共に村に残り、シングルマザーとして凌いでいた。こんな小さな村で子育てをしながら生活するのは大変だったろうが、しっかりと、今もひとりで生きている。
九十年代に入り、アルプハーラ地方は自然が豊かな山岳観光地として注目され、外国や都市部から多くの人々が移り住むようになった。廃屋が手入れされ、農作業小屋が立派な別荘に生まれ変わっていった。まあ、オレもそのひとりの異邦人といえよう。
この地方一帯は景観条例によって、どの家も石積みのままか、真白に塗らなければならない。その面倒な壁塗りは、昔から女性の仕事になっている。そこでマリアはどこの家にも出向き、壁塗りをして生計をたてていた。それに、オレや外国人の家事の手伝いもする。今は手作りタイルの工房で働いている。逞しさを実感させる女性ではないか。
村にはもうひとり、これぞシングルマザーという女性がいる。このところ肥り気味ではあるが、まだまだ容色衰えぬ四十歳になりたての熟女、マドリッドから移り住んだ国産異邦人マリベルだ。
オレはフェレイローラ村に住む前、一年ほどポケイラ渓谷沿いのブビオン村にいたが、家の裏手に壊れ果てた礼拝堂があった。そこを職業訓練学校の生徒たちが、授業として修復をしていた。当時、国の失業者対策として、歴史的建造物の修復を兼ねて授業をおこなう職人のための専門学校が、全国的に次々と設立されたのだ。そこで左官の授業を受けていたのがマリベルだった。たまたま絵を描きに出かけた帰り道、ヒッチをしたのが彼女だった。まさかそのあとで、フェレイローラ村の同じ住人になるとは、想像すらしていなかった。噂でトランペット奏者と一緒になったと聞いていたが、暫くすると、ようやく歩きだした娘と共に、村にやってきたのだ。どういう訳か、彼氏は一度として現れなかった。
アルプハーラ地方が有名になりだすと、アンダルシア州政府はこの一帯の宿泊施設の計画に助成金を出すようになった。マリベルはこのサービスを利用し、見晴らしのよい村の西端に、二軒の家を建てた。習いたての左官の技術を駆使し、何人かの若者たちと一年ほどで完成させてしまったのだ。その一軒を貸家に、一軒を自宅にしたのだ。
ある年、長老役カルロスがパコヘスス村長との意見の対立で、突然役職を降りてしまった。この仕事、ボランティアだから、なかなか引き受け手がなかったのだが、なんとマリベルが名乗りを上げた。このときは泉端談義も大いに盛りあがった。
「とうとう、この村出身者でない女性が長老役になるのかね」
棟梁フランシスコは、ツルリとした真っ赤な頭を撫でながら、ため息混じりに呟いた。
「おまえがやればいいんだよ。村のことは誰よりも知っているし、水問題が起きたっておまえのひとことで解決さ!」
元長老役になったカルロスはフランシスコにぜひ引き受けてもらいたいような口振りだった。
「やだね。政治向きの話は一切ご免被りたいし、まあ、若い人にやってもらうのはいいことさ」
「いっそ、長老役なんてないほうがいいかもよ。誰がなろうと村は変わらないし…」
酔っ払いのアウグスチンは、かなり醒めている。でも、現実は村を代表する長老役がいないことには、道路の補修から上下水道の維持管理の予算要求まで、なにもできなくなるし、結局、マリベルが長老役代理ということで納まった。
なにごとにも積極的なマリベルは、その年の九月に催される秋の文化週間に、フェレイローラ村も参加すべく催事計画を村役場に提出した。こんなことは前代未聞である。村のレアル通りを利用して、野外絵画展をしようということだった。計画案が可決すると、マリベルはオレの家にやってきた。
「イシー、おまえは絵描きだから、当然参加するよね」
唐突に出品の依頼をしてきた。
「それは無理だよ。野外に絵を飾るとなると紫外線に直接晒されることになるから、微妙な色合いは変色する危険があるんだ」
「そうなの、知らなかったわ。でも、小学校の先生と相談して、子供たちの絵を並べることにしたのよ」
まったく、マリベルはこうと思ったら断固突き進む強靭な精神力の持ち主である。それでも厚紙に貼られた子供たちの自由奔放な作品が並ぶと、レアル通りもなかなか壮観であり、野外絵画展は押しなべて好評だった。子供たちの親や縁者たちがみにきてとても賑やかだったが、その年をもって催事は終了した。企画はよかったのだが、裏方の仕事は人任せだったのが村人に嫌われてしまったのだ。しかしながら、今までにはなかった新風が村に吹いたことだけは確かであった。マリベルの努力は充分評価されるべきである。
ある日、マリベルに突然の不幸が襲った。
娘が不慮の事故に遭い、六歳の幼さで急逝してしまったのだ。彼女のショックは計り知れないものがあっただろう。長老役も降り、暫くは家から出てこなかった。だが、ここからが熟女マリベル。何ヶ月かが経ち、彼女の心も癒されたのか、あまりみかけない男友達が家に出入りするようになった。と思ったら、マリベルのお腹が大きくなり、ほっぺがぷっくりとした可愛い女の子を出産した。その後、その男はやはり現れなったり、マリベルは相変わらずシングルマザーとして子育てをしながら、二十キロほど離れたランハロンの街で温泉療養所のマッサージ師として働いている。美形マリベルは、頼もしくも生命力に溢れた女性である。
マリアやマリベルだけでなく、アルプハーラ地方には余りにも多くのシングルマザーがいる。行政面からの特別援助でもあるのかと、行政区ラタアのパコヘスス村長に聞いてみた。
日曜日の午後、作ったばかりの桑の実ジャムを持参し、ピトレス村に住む村長の家を訪れた。村の広場を離れ、山側に向かって急坂を登る。途中、栗の古木が小路を覆うように生え、木陰が縞模様に続く。路に面した門柱をくぐると、長いアプローチがあり、谷側にはクルミ林、山側にはラズベリー畑が広がる。南面の見晴らしのよい傾斜地に、石積みの瀟洒な家が木立に隠れるようにあった。残暑の残る九月だというのに、冷涼な風が渡る。ここの標高は千三百メートルを優に超えている。
パコヘスス村長はすぐに現れた。玄関前の芝生は散水してあり、深いテールベルト色に光っていた。そのなかに白い椅子が並んでいた。握手をし、近況報告しながら座り、雑談が始まった。遅れてカミさんのカルメンが現れた。鄙稀美人なのは当然、カタルニア地方の血を受け継ぐグラナダ生まれである。飲み物を聞いて、再び家のなかに消えた。
「なぜアルプハーラ地方にシングルマザーが多いかという話ね。カソリックの教義からいったら、まあありえない女性像だけど、時代が変わったとしかいいようがないよ」
「行政からの特別援助があるとか…」
「確かにスペインでも出生率が下がり続けていて、ようやく去年、前年比を上回ったんだけど、皮肉にもマグレブ地方からの移民たちがせっせと子作りをしたおかげだったんだよ。そこで、今年から三歳までの子供には毎月百ユーロほどの養育費が支給されるようになったんだ。でもこれは誰にでも平等だからね」
確かに邦貨一万四千円では援助の域を超えていない。他にも理由がありそうだ。そこで村長は、日本女性との感性の違いを語りだした。彼は合気道の勉強のため来日し、カルメンと一緒に五年ほど滞在したことのある親日家で、日本の実情については、彼なりの見識をもっている。
「スペインの女性は、とにかく独立心というか自意識が強いかな。このところ地域の女性活動家が増えているし、フェミニスト運動は根強いものがある。たとえば、国会議員の三人か四人にひとりは女性だし、アンダルシア政府にいたってはほぼ半数になる。裁判官も三人にひとりだよ。これはなにもスペインだけでなく、ヨーロッパ全体に云えること、北欧ではもっと比率が高くなる。女性の意識の強さと、それを容認する社会があるからかな」
麦茶を手渡してくれたカルメンも深く頷いた。それにしても経済的基盤なしに生活することはできない。
「アルプハーラ地方に、外国人が増えたことが影響しているとは思いませんか? 皆、よく家事の手伝いを頼んでいるし、シングルマザーには好意的だからね」
オレの言葉に村長はニヤリと笑い、肯定も否定もしなかった。彼女らにとって、手馴れた家事が仕事になり、豊かな自然のなかで子育てができるのは、経済的には苦しいが、女性としての安寧が得られる、かけがえのない環境なのかもしれない。帰りがけ、カルメンの作ったお手製マーマレッドを貰った。クワの実ジャムのお返しである。
スペインという国は、十五世紀末、カスティリャ国のイサベル女王と、アラゴン国のフェルナンド王が結婚したことにより誕生した。当初から女性の力が欠かせなかったようだ。
マリアとマリベルも、会えばいつも屈託のない微笑みで挨拶をする。久し振りに日本から帰ってくれば、頬にキスをして無事の再会を喜んでくれる。彼女らをみていると、男と女の新たな関係が暗示されているようだ。鄙びた小さなフェレイローラ村でありながら、時代を先取りする女性たちに、将来を託されている気がする。 |
|
|