|
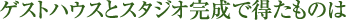 |
|
野生のブラックベリーが刈り払われ、昔の姿を現した廃屋は壁が落ち、なんともみすぼらしい姿だった。この廃屋はもう三十年以上、人が住んでいなかったという。なかに入ると、すえた匂いがし、床には灰色の雪のようにホコリが積もっている。小さな窓から差し込む光が低い天井に反射し、淡く家のなかを照らしだし、昔の住人の生活を思い描かせた。権利書によると、この廃屋は一九二七年に登記されていた。
棟梁フランシスコが、ようやく動いた。
ツルハシを持った見習い格の若棟梁ペドロと畑の師匠ホセ、それにホセの長男が二階に上がり、床に穴を開けだした。ホコリが舞うなか、鉄平石やら栗の木の小割りが一階に降り積もっていく。作業が一段落すると、庭師ペペゴルドと酔っ払いのアウグスチンがネコ車で外に運びだす。アウグスチンはシナトラの古い歌を口ずさんでいた。廃屋への鎮魂歌のようでもあり、再生への喜びの歌にも聞こえた。二階の床に穴が開くと、今度は屋根に登り、同じ要領で穴を開けていく。栗の太い丸太の梁が現れると、棟梁と若棟梁が鏨とハンマーを使い、壁に埋め込まれている両先端を掘り起こしていく。抜ける状態になったら、梁に太い荒縄を結びつけ、全員でゆっくりと下ろしていくのだ。単調な作業ではあるが、力仕事の連続だった。
ここで皆の仕事振りを紹介したい。
まず、朝一番に居酒屋アルヒーベに立ち寄り、ブランデイ入りカフェを飲む。体の芯から柔軟にするためだろうか。ともあれ、これが彼らの体調管理方法なのだ。大体八時から仕事を始め、十時半から三十分間休憩をとる。家から携えてきた布袋からパンと腸詰めを取りだし、いつもポケットにしまわれている折りたたみナイフで、器用に引き切りして食べる。そして、地酒ビノコスタを革袋から絞りだしながら飲む。それから二時まで仕事をし、五時までの三時間が昼食兼シエスタになり、五時から二時間仕事をし、一日が終わる。帰りには必ず居酒屋アルヒーベに立ち寄るから、一日何回地酒ビノコスタを飲むのだろうか…。賃金は一週間ごと、週末に払う。金額は棟梁で一日邦貨八千円、見習いは六千円だった。彼らの仕事振りをみていると、労働とは汗をかいて稼ぐもの、汗は地酒ビノコスタで補うものといった考え方のようだ。
工事が始まった春から夏、そして秋が終わろうとしたころ、棟梁の癇癪が起きた。実は棟梁、かなりの癇癪持ちなのだ。気の毒なのは見習いをしているホセの長男である。セメントの練りが足りないとか、仕事の後始末が悪いとか、まあ文句はいくらでもあるのだが、その云いかたがきつい。いつも頭ごなしにどなりつけるのだ。父親のホセはスペイン人には珍しい無口な男である。それに、息子の仕事ぶりには頼りなさを感じていたのか、棟梁の癇癪をみてみぬ振りをしていた。繊細な心の持ち主、長男には耐えられなかったのだろう、仕事を放り投げて家に帰ってしまった。そこで登場したのが、なんとホセのかみさんだった。工事現場にどなりこんできたのだ。
「フランシスコ、それでもおまえは棟梁なのかい。見習いいじめはいい加減にやめなさい!」
「なに云ってんだいカルメラよ、仕事がのろいから云ったまでだ!男の仕事に母親が口なんかだすんじゃない!」
哀れ無口な畑の師匠ホセこと旦那は黙ったままである。アルプハーラ訛りの早口でいい争うふたりに割ってはいるほど、オレは会話に自信がないし勇気もない。その剣幕にただただ怖気づくばかりだった。あわや取っ組みあいの喧嘩になるかと思いきや、沈黙がながれる。お互いの主張が明確になったところで争いごとは終結する決まりだ。スペイン流の揉め事結審の儀式だと思えばよい。結局、長男の代わりに、十七歳の次男が働くことになった。十六歳までの義務教育を終え、家でブラブラしていたのだ。父親似で無口、オートバイ好きで、時間があればモトクロス用バイクに乗っていた。その次男は棟梁の癇癪が落ちても動ぜず、最後まで仕事を続けたのには驚いた。
二年目の初夏、百本近くあった梁がすべて取り払われ、厚さ一メートルを超える壁だけが残った。壁は漆喰や石灰で塗られた白の他、その昔に塗られた青や黄土色が覗いていた。梁が抜かれた大きな穴が左右対称に規則正しく並んでいる。天を仰ぐと、真青な空が四角い壁に縁取られてみえる。まったく、現代彫刻を思わせる世界があった。
長かったがようやく、ここにきて建築作業が始まることになる。いままでは取り壊し作業だったのだ。
棟梁フランシスコと、ひとつひとつ必要な建築資材とその量を打ち合わせ、ピトレス村のアラゴン商会に発注する。例の果樹園になった畑をオレに売ったロベルトが社長をしている会社だ。面白いことに、建築資材の発注は施主がおこなう。経費が正確に把握できる利点はあるが、作業の段取りをみながら棟梁と相談してアラゴン商会に出向かねばならず、忙しい思いをした。しかし、このおかげで家造りに参加できた気分になれたし、至福の喜びを味わえた。建築資材は、荷台が青と白のストライプに塗られたダンプトラックで、何日かおきに陽気なヒゲ男が運んでくれる。荷台を油圧で持ち上げると、レンガや砂、セメント袋が水車小屋跡にある小さな空地に山積みされる。これが二年半、毎週のように続いたのだ。
壁だけになった元廃屋の周囲に、栗の細長い丸太を使って足場が組まれた。そこを地酒ビノコスタを飲んで顔を赤くしている左官屋衆が、こともなげに登っていくから不思議だ。幸運にも最後までだれひとり落ちた者はいなかった。
棟梁が見習いを壁の天辺まで登らせ、分銅のついた糸を下げさせ、垂直線を計る。それに合わせて鉄の長い定規を漆喰で固定する。これを壁の両端でおこない、二本の定規を糸で結び垂直面を知る。これを目安に不必要な壁面のセメントなどを取り去り、梁の抜けた穴や傾いた壁をレンガで埋めながら修正していく。面白いのは、壁面と壁面が直角である必要はないことだ。だから、どの部屋も正確には真四角形でない。極端にいえば、菱形になっていたり台形になっていたりする。これは、家を建てるとき、地形に添って造るからだ。傾斜地に建てられれば、部屋ごとに床の高さまでが違ってくる。唯一、細心の注意を払うのは、壁面が垂直に立っていることである。スペインの集落が美しくみえるのも、このように自然の立地条件に合わせて家を建てるからだろう。
壁面がしっかりできあがると、次に二階の床を造る。廃屋の天井高は二メートルほどだったが、二メートル四十センチに上げた。天井は高いほうが圧迫感がなくてよい。壁の高さは一階と二階を合わせて八十センチ足りなくなる訳だが、レンガで壁を積み増しすればよい。次は、新しく梁を埋め込む高さに、鏨とハンマーで穴を開けていく。そこに、鉄線で補強されたセメント製の梁を差し込んでいくのだ。梁と梁の間には、専用のブロックをはめ込み、床の基礎ができる。その上にセメントを塗り、タイルを貼れば床ができあがる。一階の天井側はセメントを塗って仕上げる。窓や扉は、開口部の上側にセメント製の梁を寸法に合わせて切って、埋め込む。それから、鏨とハンマーで石壁をはつって窓の空間を作る。大きな窓など、開口部を多くしたため、この作業は想像以上に時間がかかってしまった。それにしても、亀の歩みのような作業が毎日続いた。途中、アーモンドやオリーブの収穫だとか、灌漑用水路の補修事業があれば、工事を中断して休んだ。それに若棟梁ペドロは、よく遅刻してきて棟梁の癇癪が落ちていた。実はそのころ、ペドロはサラマンカから現れたスレンダーな美人と恋仲になり、ふたりで居酒屋アルヒーベにいりびたっていたのだ。彼女はこのあたりでは有名な酒豪だった。ペドロと付き合えるのは、彼女の他に居なかったのかもしれない。それでも作業は進んでいたのだが、突然大事件が発生した。
ある日、現場にいくと、どこにもだれもいなかったのだ。練られたセメントは黒いゴム製のバケツに入ったままだし、コテはセメントの付いたまま放りだされていた。なんだか、神隠しにでも遭ってしまったようだった。それにしても、なにが起こったか見当もつかなかった。まずは棟梁の家を訪れることにした。入口の扉を押し開け、声を掛けると二階からいつものように彼が低い声で答えた。
「上がってこいよ」
オレの心配をよそに、なんとも落ち着いた声である。それに、昼飯まえだというのに、もう地酒ビノコスタを飲んでいた。さすがにかみさんの手料理が間に合わなかったのか、腸詰めのモルシージャをつまみにしていた。ポケットにしまわれている折りたたみナイフで切り取りながら、手でちぎったバゲットと一緒に頬張っている。モルシージャとは、豚の血をタマネギと混ぜ、ナツメグをきかせて腸詰めにし、茹でて天火で干した、手のこんだ一品である。英語でいうブラッドプディングだ。真っ黒でみた目は悪いが、これを軽く火で炙り、柔らかくなったところをパンに挟んで食べると、ナツメグの香りと共に、肉の甘さが口中に広がる。早速、かみさんがオレのためにも用意してくれた。
「どうなってるんだい。現場に行ったら、だれもいないし、仕事は放りっぱなしだし、驚いたよ」
「まあ、一杯飲め。いま隣村のメッシーナから連絡があってな、労働監察官がやってきたというんだ。こんなところまでやってくるとは思わなかったよ。だから皆には隠れてもらってるんだ。ペドロはどこかで昼寝しているよ」
このあたりでは、失業保険の給付を受けていながら、陰で仕事をしている者がいる。どうも全国的なことらしく、その取締りを専門にする労働監察官がいるのだ。それがこの村の近くに現れたというから、大騒ぎになったのだ。実は若棟梁ペドロが失業保険の給付を受けているひとりだった。それにしても村人同士の連絡網は驚くほど緊密で早い。おかげで皆が助かり、喜ぶべきことだったのだ。
「労働監察官がこのあたりまで現れるとなれば、合法的に仕事をしなければならないな」
「というと、具体的にはどうすればいい?」
「おまえが、この工事に限って請負業者になるのさ」
後日、棟梁に紹介された司法書士の事務所を訪れた。書類を揃えて厚生労働省に申請したが、当然ながら受理されなかった。実はオレは観光ビザで滞在していたからだ。ところがさすがスペイン、司法書士の耳打ちがきいたのか、次には認可が下りてしまった。必然性は法的規制をも乗り越えるのだった。晴れて工事は公に再開された。しかし、若棟梁と見習いのふたり分、社会保険料をオレが支払うことになり、賃金は一挙に五割増になってしまった。
ゲストハウスとスタジオが家としての輪郭をみせ始めたころ、今度は棟梁とオレが衝突してしまった。問題は家の周りに生えていた三本の木だった。
「イシー、サクランボの木がじゃまだから切るよ」
工事現場に行くと、棟梁フランシスコはいまにも切り倒す寸前だった。
「ちょっと待ってよ。切らなくてもどうにか作業はできそうにみえるけど…」
裏の畑側にはサクランボとビワの木が、水車小屋跡にはイチジクの古木が生えていた。毎年実を結び、小鳥たちや酔っ払いのアウグスチンまでが甘露な味わいを楽しんでいた。
「どうにか切らないで済む方法はないかね?」
「おまえな、木はまた植えれば大きくなるし、こだわることなんかないよ」
確かに棟梁の云うとおり、村人の植物や動物への感性はオレとはかなり違う。彼らにとっての生き物とは、村人の生活を潤す存在でなくてはならない。それでなければ、一年間丹精こめて育てた豚を屠って食べることなどできないだろう。古い果樹は若い苗木に植え替えて、たくさんの果樹を収穫しなければならないのだ。残念ながら、古木を愛でるといった情念は少ないようだ。しかし、施主のたっての願いということで、三本の木は切られずに済んだ。ところがサクランボの木は枝が払われ、とうとう足場の一本として使われ、ビワの木は基礎工事にさしつかえると、根の半分以上が切り捨てられてしまった。イチジクの古木だけは、建物の一部を削ってまで切らずに済ませたから、棟梁は最後まで文句をいい続けていた。
工事を始めて四年目の春を迎えるころになると、ゲストハウスとスタジオは完成を予想させる佇まいになってきた。そして、ようやく細部に手が付けられた。棟梁は専門職である給排水や集中暖房の配管工事に移った。若棟梁には、得意だという暖炉工事をしてもらった。暖炉は煙突部分を含めて、細心の注意が必要だった。失敗すれば、煙が逆流したり、熱効率が悪くなってしまう。
仕上げが近づくと、左官屋衆ではできない仕事が多くなり、近在の職人や工芸家に力を仰ぐことになる。まず、ピトレス村に工房を持つ木工師に窓や扉、クローゼットや台所のカウンターなどを頼んだ。洗面所には大理石を使ったので、タブローネス村の石工を呼んだ。電気工は、ブビオン村からやってきて、配管や暖炉の位置を確認しながら壁をはつり、電線を通すパイプを埋め込んでいった。窓やテラスの戸に、オルヒバの街からやってきたガラス屋が特注のカットガラスをはめていく。俄然家らしい表情がでてきたが、スペインではもうひとつ、大事な工程が残されている。泥棒よけの鉄格子が一階の窓に付けられなければならない。この鉄格子は建物のファサードを飾る装飾でもあり、公共の建物や大邸宅ともなれば、唐草紋様に家紋がはいったりしてかなりデザインの凝った作りになる。オレはポルトゴス村に居る鉄細工師に頼み、簡単な唐草紋様ながら昔ながらの工法であしらったデザインを注文した。これでようやく外装工事は終わる。内装工事は、若棟梁ペドロが丹念にタイルを貼っていったあと、台所や洗面所の器材を設置して終わる。それから、各部屋に必要な家具はカピレイラ村の家具職人に栗の木を使ってオーダーした。スタンドなどの照明器具は、ブビオン村に住むフランス人の女性織物師に頼んだ。家を建てるには、多くの人たちの協力が必要だということが身に染みてわかった。
さて、家具などがくるまえに、家は最後の化粧をする。家の外も内も白く塗られるのだ。フェレイローラ村でフラメンコの先生をしているペパとそのお弟子のシングルマザー、マリアのふたりが、鼻歌まじりで真白に仕上げてくれた。そして、家具などが置かれると、名実ともにゲストハウスとスタジオが完成したことになる。
泉端会議で廃屋が売りだされていることを知ってから完成まで、ほぼ五年の歳月が流れていた。今では村の景観にも馴染み、レアル通りの一角を占める存在になっている。棟梁フランシスコに枝を切られたサクランボの木は、以前にも増して枝を伸ばし、枯れかかったビワの木は萌黄色の若葉をたくさん付け、イチジクの古木はなにもなかったかのように、毎年甘い実を付けている。猫たちも、イチジクの古木からゲストハウスの屋根に登り、愛の駆引きをしている。すべてが村の一部となり、日常生活のなかに同化したようだ。若棟梁ペドロは、あいかわらずの酔っ払いではあるが、近在の村では棟梁として認知され、恋人と結婚し、元気な赤ちゃんを授かった。畑の師匠ホセの家では、運搬用トラクターを購入し、二人の息子は運転手をしながら左官工として働き、なかなかの稼ぎをしているという。そして、尊敬する棟梁フランシスコは仕事を辞め、悠々自適の年金生活を送りながら、畑仕事を楽しんでいる。オレはといえば、一緒に家造りに携わった職人たちの仲間入りを果たした。総面積百五十坪の廃屋に費やした資金は七千万円を超えてしまった。日本で家を建てたとしても決して安い金額ではないが、ここスペインではそれ以上である。オレにとっては大きな出費だったが、それに見合うものだった。建物が完成した喜びの上に、多くの友達を得ることができたからだ。そして、ようやく村人のひとりとして認められたようだった。
|
|
|