|
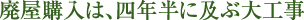 |
|
廃屋を買うに至る話をしよう。ほとんどの村人が、毎日のように通う路がある。サンタクルス広場から東へ緩やかな下り坂になり、村を抜けて五分ほどのところにある自然の泉に向かう路だ。弱い炭酸水が自噴する、サンタパウラの泉である。この天然のミネラルウオーターは誰もが体によいと信じているので汲みに行きがてら散歩をするのが村人の日課になっている。この路はレアル通りと呼ばれ、村の本通りでもある。といっても、賑やかな繁華街ではなく、商店も居酒屋もない。その代わり、リンゴやオリーブの枝が路にせりだす、風情ある通りになっている。このレアル通りは村のメインストリートだけあって、畑の師匠ホセ、長老役カルロス、棟梁フランシスコ、元教師ドンマヌエル、それにオーストラリア人のボブなどの住む家が連なる。こんな重要な通りに一軒、廃屋があった。その昔は小麦を挽いていた水車小屋だったのだが、水車の部分は壊れ、石組みを残すだけになっていた。水車脇には大きなイチジクの樹が野放図に葉を広げ、裏庭には一抱えもあるサクランボの大木が生えている。廃屋は野生のブラックベリーに覆われ、絵になる姿ながら、なんとも寒々しい佇まいを晒していた。当然、廃屋だから誰も住んでいないのだが、棟梁フランシスコのラバが居候していた。そんな廃屋が売りにだされたことを、いつもの泉端談義で知った。村に住み始めて五年が過ぎようとしていたころだった。
そのころ、日本から訪ねてくるお客が増えるようになり、なんだか家も手狭になってきたし、それに揮発性の強いテレピン油で絵を描いているので、家中匂い頭が痛くなって困ってもいた。もしこの廃屋を買い、仕事場兼客間として使えたら、こんな問題は一気に解決する。それに村のメインストリートから廃屋が消えれば美観上からもよい。善は急げと買い取ることにした。これが四年半にも及ぶ大工事になるとは、そのときは想像すらしていなかった。
いつものように泉端談義の輪に加わっての村人とのおしゃべりからすべてが始まった。
「あの廃屋、売りにでてるんだってね」
「そのとおり。誰が買うのか興味のあるところだけど、まさかオマエが買うつもりかい?」
長老役カルロスが興味深そうに答えた。
「あの廃屋はいい場所にあるし、直して売れば商売になるよ」
棟梁フランシスコは、地酒ビノコスタで顔中真っ赤にしながら言葉をつないだ。彼は果樹園にした畑を買ったときも、こそっと車庫をいくつか建てて商売しろと話していた。なかなかの商売人である。
「いやあ、商売は考えてないよ。ただ、お客さんが多くなったし、ゲストハウスにでもしようかと思って…」
「そうかい。ゲストハウスとやらにするなら、裏の畑も買ったらどうだい。昔の村役場跡も一緒についてくるぞ」
棟梁フランシスコが興味深い情報を教えてくれた。数十年まえ、まだフェレイローラ村に五百人近い住民がいたころは、隣のアタルベイタル村と二村でひとつの行政区だった。そのときの村役場跡と裏庭のように隣接している畑の持ち主が同じだったのだ。大いに興味が湧いた。もしこの畑と村役場跡を買えば、L字に二軒が並んでいるので畑が中庭のようになる。一軒をゲストハウスにし、もう一軒をスタジオにすれば理想的な制作環境にもなる。早速、長老役カルロスに頼んで、それぞれの持ち主に声をかけて売る気があるかどうか聞いてもらった。
それから半年後、ようやく二軒の廃屋と畑の売買契約書にサインができることになった。これもグラナダに住む弁護士セラーノ氏のおかげである。スペインで不動産を買うときは、弁護士の助けを借りて権利関係を確認してもらい、売買手続を代行してもらうのが一般的である。母屋を買うときも彼に手伝ってもらった。特に田舎の古い家などは、一族の共有物件が多く、皆の承諾を得るのは、外国人の手に負えることではない。今回もセラーノ氏の尽力により、書類を揃え、契約するに至った。持ち主のひとりは、牛追い祭りで有名な北部バスク地方パンプローナに移住していた。セラーノ氏の呼びかけで、久しぶりに故郷の夏祭りをみがてら契約するために出向いてくれた。その日、セラーノ氏のはからいで、グラナダ市内にある司法書士の事務所で売買契約をすることになったのだが、約束の時間に行くと、賑やかに一族の十人近くの人々が待っていた。そこで代表の老夫婦とともに売買契約書に署名し、権利書をもらい、小切手を渡した。それから慣例に従い、皆で近くの居酒屋に繰りだした。売り手のおごりで乾杯し握手をしてお互いを祝福しあい、本当の意味での契約を終えた。長らく廃屋だったとはいえ、故郷の家を手放すのだ。彼らの人生の大きな節目になったことに違いない。その日の契約は、心の旅立ちをおこなう盛大な儀式だったのだ。オレにとっては、水車小屋跡と村役場跡、それに年季のはいった梨の樹が生える畑まで受け継ぐことになった。
家を建てる。これはスペインといえど大事業である。だから、都会では建築業者に頼むのが普通だが、田舎では左官屋の手を借りて、自分でコツコツ建てることがよくある。ちょっとした改装工事などは、当然のこととして日曜大工よろしく仕上げてしまう。だから村の男たちは、誰もが準左官屋と呼べるほどの腕前をもっている。でも、不慣れなオレはセメントや漆喰をコテで塗る作業となると自信がなく、プロの左官屋に頼むしかなかった。
フェレイローラ村にはふたりの優秀な棟梁がいた。ティトとフランシスコの両巨匠である。もう一人、オーストラリア人のボブもプロ級の腕前なのだが、仕事としては請け負わない。古い家を買ってセンスよく手直し、転売することを商売にしているからだ。となると、ティトかフランシスコに頼むしかない。テイトはその昔、長老役をやったり、カミさんに居酒屋をやらせたり、なかなか多才な棟梁だった。ところが村に仕事が少なくなると、グラナダ市内に住む娘夫婦の家に移り住み、そこで庭師になってしまった。となれば、フランシスコしかいない。村では水道屋のフランシスコと呼ばれており、上下水道やガスの配管工事については、彼の右に出る者はいない。頭はつるりと禿げあがり、いつも赤ら顔、背は低く腹のでた六十歳台。スペイン人の典型的タイプで、地酒ビノコスタの信奉者でもある。野良仕事が大好きで、左官の仕事が終わった後でも、ラバと共に畑にでかける。機械類に滅法強く、愛車の古いシトローエンなどは自分で修理するし、草刈り機からチェーンソーまで、なんでも直してくれる。彼と飲んでいてその理由が判った。
「いやあ、兵隊のときモロッコの駐留軍にいたんだけどね、戦車隊の工兵だったんだ。そのときの経験が役立ってるわけさ」
幅広く仕事をこなすし、とても興味深い棟梁だった。迷わず彼に棟梁職をお願いすることにした。家の工事は無理に急ぐこともなかったし、まずは楽しく、彼と一緒に家造りを一緒にしたかった。実は、もう二十年近くも前のことなのだが、南房総半島の突端に、友人とふたりで、それこそトンカチ、ノコギリを使って一年あまりで家を建ててしまったことがある。日本に帰ればいまでもそこに住んでいるが、まだ健在である。そのときの経験から、家造りとはなにか、大体の輪郭がわかっていたこともあり、なんとなく作業工程がみえていたし、自信もあった。おかげで、スペインでもういちど家作りの貴重な経験ができたのである。
工事を始めるにあたって、いささか驚かされたことがあった。苦心して図面を仕上げ、棟梁フランシスコの家を訪れると、しばしそれをみていた棟梁がぽつりといった。
「うーん、わかんないな。オマエがいつも描いてるように、絵にしてくれるとありがたいけど」
なんと棟梁フランシスコは図面が読めないのである。また、自分のサイン以外は字も書けないときている。それからは、それぞれの現場の完成図を絵にし、そのなかに寸法を加え、説明しながら工事を進めていった。その方法のおかげでよりシンプルに工事ができたことは確かである。でも、文字通り手造りのおかげで、完成まで四年半の月日が流れてしまったのだ。最終的には畑をハーブ園にしようと考えているのだが、まだ未完成のままだから、厳密に工事が終わったとはいえない。しかし、建物二軒の工事が終わったところで、棟梁フランシスコは隠居してしまった。最後の仕事としてオレのゲストハウスとスタジオの家造りを選んでくれたわけだから、深く彼には感謝している。
さて、工事が始まるまでにも、あれやこれや雑用で時間が流れていった。あたりまえの話だが、スペインの田舎といえど、建築確認申請を村役場に提出しなければならない。しかし廃屋だったので、家の修理扱いになり、複雑な書類は必要なかった。このあたりは、国定公園に隣接している村だけに、新築だったら大変な量の書類を準備しなければならなかった。おかげで、簡単な図面と工事見積もりを提出し、その工事金額の五パーセントを村税として払うことで済んだ。廃屋の購入は、大正解だったといえる。弁護士セラーノ氏の尽力で複雑だった権利書も整い、村役場から工事の許認可も受けられたのだが、現実はもうひとやま問題を残していた。
まず、棟梁フランシスコもこの廃屋の持ち主のひとりだったのだが、正式に譲渡契約を交わしたにもかかわらず、あいかわらず彼のラバが居座っていた。それに村役場跡の廃屋には、畑の師匠ホセのかみさんカルメラが、収穫した大量のタマネギを置いたままで、一向に持ち去る気配がない。腐っているタマネギは悪臭を放っていた。いつまでたっても状況は変わらないし、工事も始まらない。そこで、棟梁フランシスコの家を訪ね、地酒コスタを飲みながらの交渉となった。
「やあ、いいときにきた。まあ、一杯飲め」
お決まりのワインタイムの始まりである。棟梁はいつものように、かみさんの手料理で地酒ビノコスタをゆっくり飲んでいた。タパは豚の内臓料理、カージョである。スペイン料理には珍しく、ピリッと唐辛子をきかせ、ニンニク、トマト、それにパプリカで風味と色をつけた一品だ。むっちりした田舎のバゲットをちぎり、赤いソースをつけながら食べると、地酒ビノコスタが止まらなくなる。早速、かみさんがてんこ盛りのカージョとガラスのコップに満たした地酒ビノコスタを運んできた。
「いやあ、カージョは大好物でね。それにかみさんの手料理はいつも絶品だね」
これぐらい誉めるのがスペイン流。彼女もまんざらではない表情をする。注意しなければならないのは、これ以上誉め過ぎないことである。おかわりを催促することになり、帰りには鍋一杯のお土産を貰うことになるからだ。
「ところでフランシスコ、工事はいつ始めるのかね。もう書類は揃っているし、村役場の許可はおりてるよ」
「そうだな。でもね、あれだけ大きな廃屋が二軒ともなると、どのように手をつけるか、よく考えないとね」
「それから…、まだラバは居候を続けているし、カルメラは何回いってもタマネギを運びだそうとしないんだよ。これもなんとかしてくれないかね」
「心配するな。ラバのことはね、いま新居を改装中だよ。できあがり次第、引越しするさ。タマネギのことは…、かみさんに直接いってくれよ」
「でもね、彼女はあの村役場跡がオレのものになったなんて知らないの一点張りでね」
「そうかい。じゃあ、前の持ち主はよく知っているから、ヤツからことの事情を電話させておくよ」
棟梁フランシスコは、ペナペナなデザートフォークでカージョをつついては頬張り、旨そうに地酒コスタを飲む。禿げあがった頭がじわりと赤く染まっていく。オレも杯を重ねるうちに口が軽くなってきた。
「ところで、工事の段取りは…」
「ああ、目安はついているよ。まず、オマエがいっていたように、この村か近在の者と一緒に仕事をする。それから、メッシーナ村の若棟梁ペドロにも手伝ってもらうよう声をかけておいたよ」
ペドロの名前を聞いて少し不安になってきた。
「ペドロって、あの酔っ払いの?」
「そのとおり。左官屋は皆酔っ払いだよ。飲まないと力が入らないからね」
確かに左官屋は力仕事である。毎日、石とレンガを捏ねたセメントでつなぎあわせていく。また、重いハンマーと太い鏨ではつる姿は男らしさそのものだ。左官屋仲間は朝早く居酒屋アルヒーベに集まり、ブランデイをたっぷり入れたエスプレッソコーヒーを飲んでから仕事に出かける。ペドロは他の左官屋より何杯か多めに飲むだけ、という解釈も成りたつ。
棟梁フランシスコと飲んでから数日過ぎたころ、ラバは新居に移り、カルメラは大量のタマネギをネコ車に積んで運び出してくれた。これでめでたく、二軒の廃屋と畑はオレのものだと、村人に認知されたようだ。それからは、棟梁フランシスコがいつ手をつけ始めるか、待つだけの日々になった。そして春、とうとう工事が始まった。畑の師匠ホセとその長男が、大きな鎌を持って現れた。そして、廃屋を覆うブラックベリーを端から刈りとり、一週間もすると廃屋ながら、二階建て延べ床面積百坪を超える立派な建物が出現した。
棟梁フランシスコの家に、夕方のワインタイムのご招待を受けた。工事について説明するという。訪ねてみると、もう手酌で地酒ビノコスタをやっていた。その日のタパは〔畑の焼き鳥〕と呼ばれる一品。いつもながら、スペイン人の奥様方のタパ作りの技には感心させられる。細長くて大きな青ピーマンを、ニンニクのスライスを泳がせたたっぷりのオリーブ油で、クタクタになるまで油煮し、塩・胡椒をきつめに振った簡単料理である。硬い柄の部分が小鳥の首のように突きだしていることから、〔畑の焼き鳥〕と命名されているのだ。イメージからは、とてもヘビーな食べ物のようにみえるが、輪切りにしたバゲットの上に、滴るオリーブ油を切らずに載せて口に運ぶと、地酒ビノコスタにぴったり。田舎でしか味わえないB級グルメの最高傑作料理のひとつになる。
「廃屋をよく点検したんだけど、二階部分の床、それに天井はすべて取り壊さなければいけないな。梁の栗の大木が雨に濡れて腐っていたよ。まあ、使えるのは壁だけだね。その壁も上塗りしたセメントや漆喰は一度全部剥がし、石積みだけの状態にし、傷んでいるところはレンガで補強しながら垂直に修整し直さなければね。窓枠も新しく作らないといけないかな」
こうなると廃屋の修理などとはいえない。工事は大事になりそうだ。
アルプハーラ地方の建物は、このあたりの景観条例によって外壁は白、屋根は陸屋根でなければならない。基本的には地中海一帯の建築様式である。石を積みあげ壁を作り、丸太を渡して梁とし、梁と梁の間を小割りした木で繋ぎ、その上にアルプハーラ地方では平らな鉄平石を敷き詰め、雲母を沢山含んだ土で覆って仕上げる。このため、昔は大雨が降ると雨漏りがひどかったという。いまは、石と土の間に大きなプラスチックシートを敷き詰めているので、雨漏りはなくなったが、プラスチックは十年もすると劣化が激しく、そのたびに替えなければならない。面倒くさい工法だが、これを遵守しなければ、アルプハーラ地方では建築は許可されない。
「ということは、二階の床と屋根の梁すべてを取り去るわけだ。それも大変だけど、梁にする栗の丸太を探すのは、もっと大変だと聞いているけど…」
「そうだ。梁となると五メートルの長さは必要だし、太さもそれなりにないとな。そんな丸太を百本以上集めるなんて、いまでは無理なことだよ。だから、鉄骨入りのセメント製の梁を使うことになるね」
二軒の廃屋を修理するのに、昔ながらの栗の丸太を使うことは諦めなければならない。それにしても、工事の手立ては新築を建てる二倍の作業が必要になりそうだ。なんだか、大変な修復計画ではないか。廃屋のなかに入り、崩れそうな階段を上ったとき、その難しさをつくづく実感した。 |
|
|